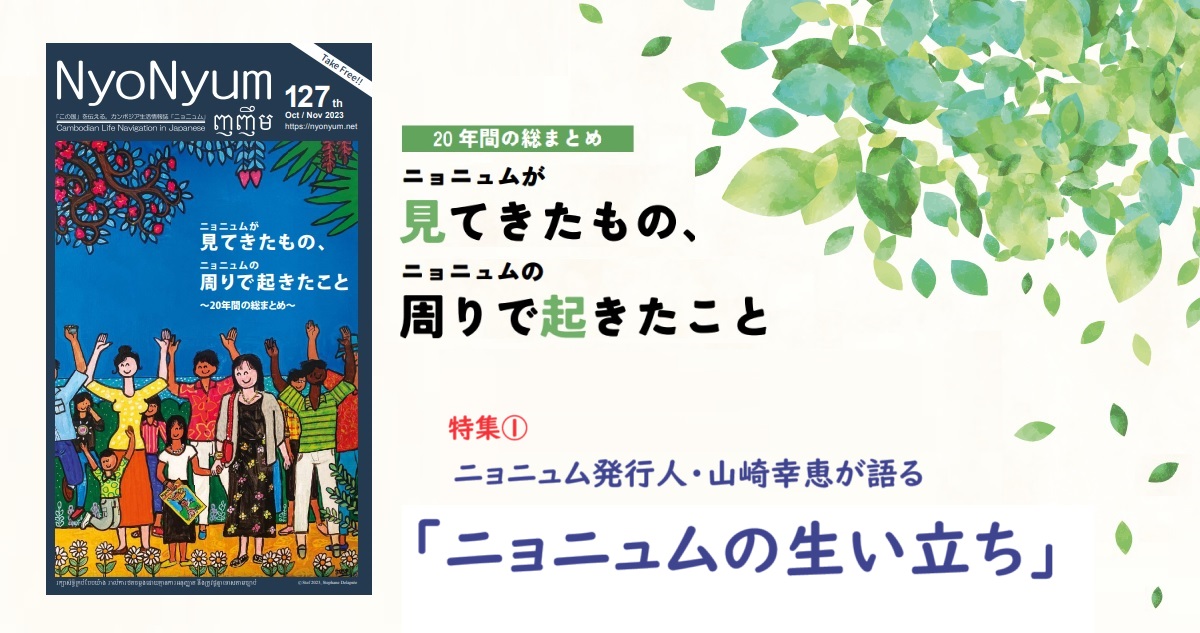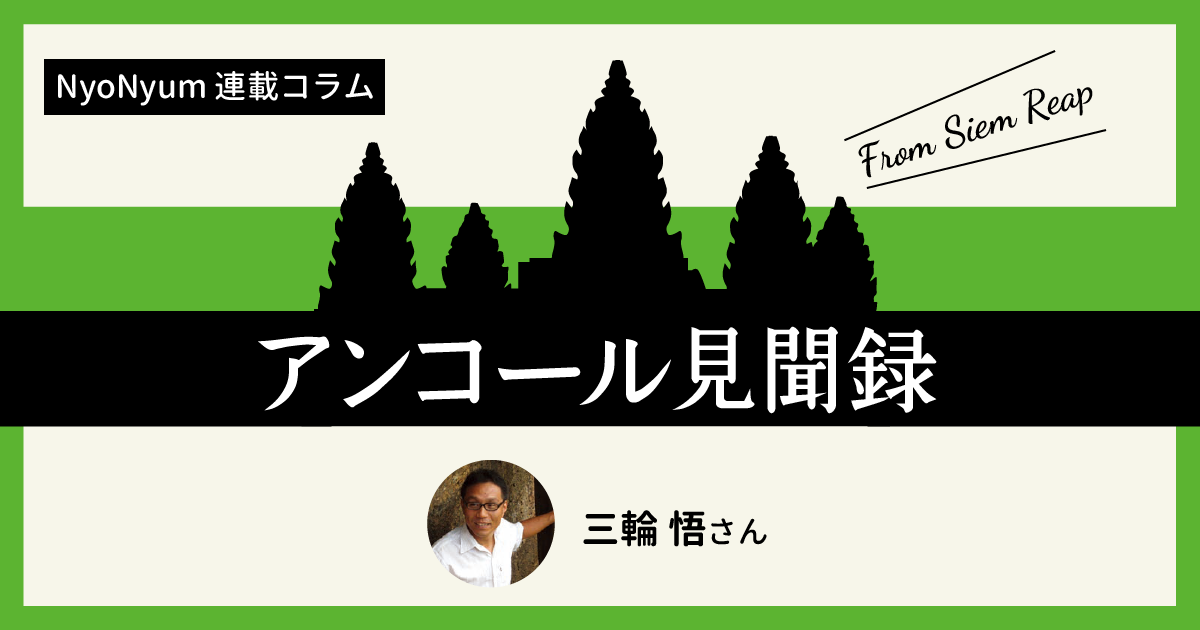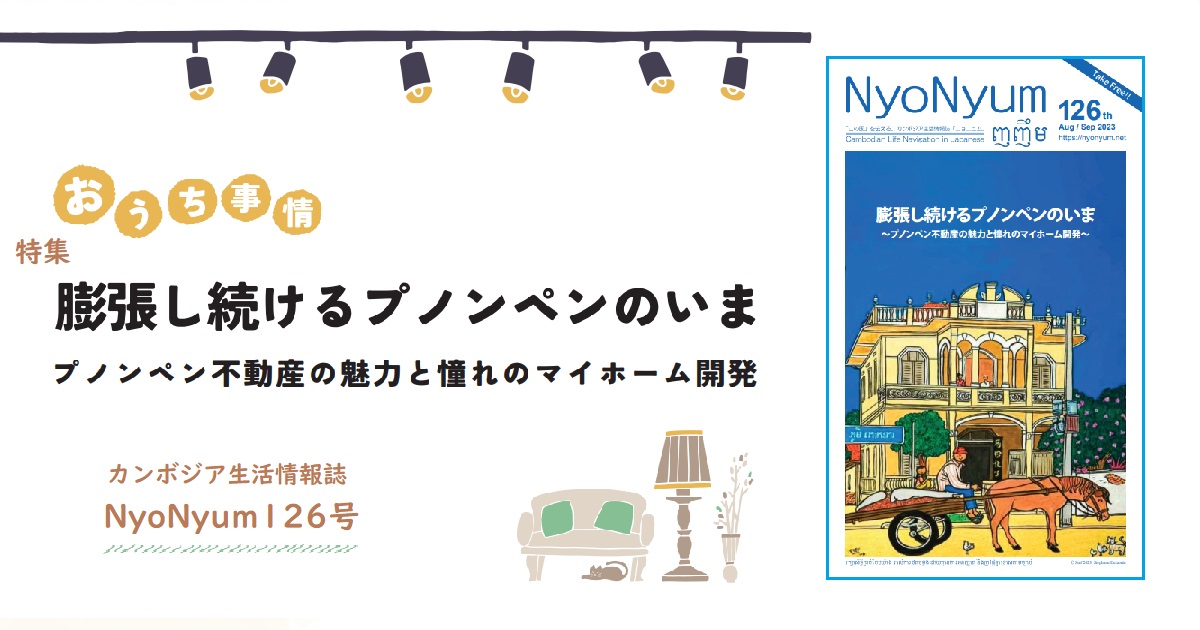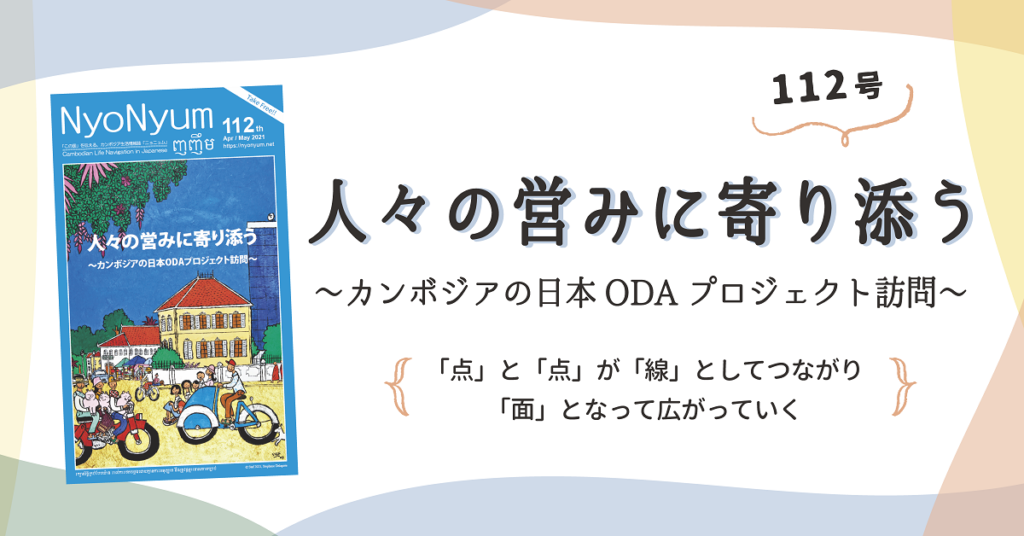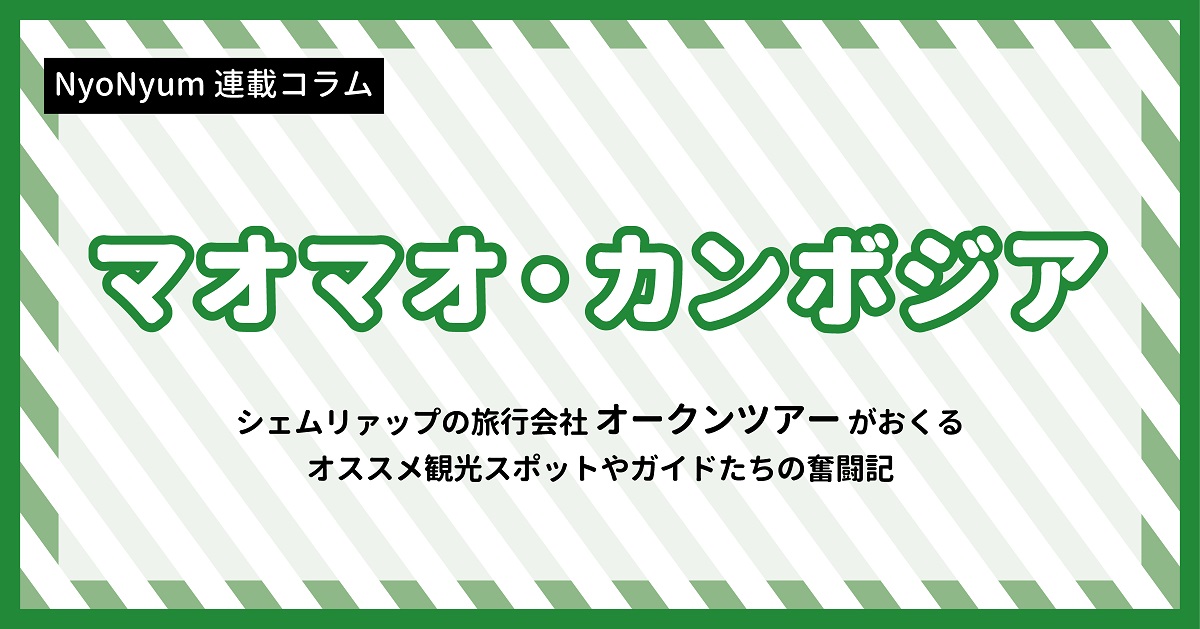「父親に励まされ、幼い頃から先進国へ留学したいと思っていました。教育があるからこそ、人は文盲や貧困から解放され、家族や社会に手を差し伸べられるのだと信じています!」「竹は竹の子から」「若者は国の柱」というスローガンを常に念頭に置きながら頑張ってきたオーク・ソヴァンナラーさん(34)は2022年に東京工科大学で博士号を取得した。カンボジアにとっての良き竹、柱になるために、日本で研究を尽くし、博士号を取得したソヴァンナラーさんが日本での留学経験と感触を共有してくれた。

ソヴァンナラーさんは2015年から2022年まで日本国際協力機構(JICA)と日本の技術支援機構からの資金援助で行われた日本とカンボジアとの国際協力プロジェクトであるトンレサップ湖の水環境をテーマに、日本の東京工科大学で研究をしていた。日本は教育部門で学生に質の高い教育を提供しており、日本の大学が世界ランキングに名を載せていたため、修士号と博士号を取得するため日本の大学で研究をすることを選択し、その魅力について次のように述べてくれた。「日本の大学院で学ぶことの特徴は、学生が最新の実験を十分に行うための実験室が十分に整備されることです。そして、大学には、学部生と大学院生、博士課程の学生が授業や研究の時間外に自主研究を行うための研究室もあります。この研究室には、一人の指導教員がおり、週に1回または2週間に1回のグループミーテイングで助言やフィードバックをしてくれたり、学生に研究の結果発表をするように奨励したり、その研究や実験の結果を地元または国際的な学術学会で発表する機会を与えてくれます。さらに、学生が研究・実験したあらゆる結果を地元または国際的な雑誌に記載することも可能だという魅力があります。この研究プロジェクトを通じて、科学論文、専門書、政策提言などの出版のための準備をしたり、科学界に利益をもたらす上に、カンボジアにおける研究開発と人材育成に貢献し、社会経済学や流体力学、水化学、微生物学、生態学、衛生、ガバナンスと管理の実践など、多くの重要な分野など幅広い研究が対象だったので、とても有意義な研究生活を送っていました。」

カンボジアは、経済が勃興している国で高い経済成長率を誇る急成長国である。そのため、国家発展のための科学研究分野における人材が求められている。カンボジアの開発に科学研究は不可欠だとソヴァンナラーさんは強く訴える。「開発を持続可能なものにするためには、事前に調査と分析を行われなければなりません。そして、自然保護を見過ごすことなく、環境、経済、社会などあらゆる角度とその深さを考慮する必要があります。先進国では常に科学研究に細心の注意を払っています。そして、国レベル及び地域の開発政策決定をするために、証拠に基づいた研究が行われています。だからこそ、日本の大学での研究所は、カンボジアを含む国内外の持続的な発展と開発の基礎となるし、国としても科学研究紀要の発行・出版も重視しているのです。」
日本への留学環境についてソヴァンナラーさん、生活に適応する上での様々な問題解決を自らしなければならないという。「当然のことながら、私たち留学生は家族から距離を置き、新しい社会、文化、伝統の中で生活するので、そのような環境に適応しないといけません。母国語ではない日本語とか英語とかでコミュニケーションをしないといけませんでした。だが、頑張っていくと新しい生活環境に徐々に適応することができました。」

勉強と日常生活のバランスに関しては、自分自身の時間だけでなく友人との時間をもつことが重要だと振り返る。「私の場合、勉強と研究の以外の週末はたいていカンボジア人の友達に会ってカフェに行ったり食事に出かけたり、祭日は日本のさまざまな観光地を訪れたりして過ごしていました。さらに、日本の生活をより深く理解するためにボランティア活動にも参加したり、日本人の家にホームステーさせて頂いたりしていました。このような学外活動は、勉強と研究で忙しい日々から心身をリラックスさせてくれたし、新しいことを学ぶ意欲を持たせる要素ともなっていたのです。」
約7年にわたる日本での生活と留学の経験を通じて、日本人が仕事に徹底的に取り組み、責任感も高く、諦めずに一生懸命に働くことを地肌で感じたというサヴァンナラーさん。良好な協力を好む文化とルールの尊重は、クメール人が日本から学ぶべきものだという。日本で経験したことを活かして、現在、カンボジアの工科大学(ITC)でカンボジアの学生に科学や研究の在り方を共有し、多くの若者が科学をもっと好きになり、これまでの自己の研究成果が自国の持続可能な発展・開発に貢献できることを期待しているという。

プロフィール:
 2013年にプノンペン王立大学の外国語学部(IFL)を卒業し、教育専攻の学士号を取得した。2014年にカンボジアの工科大学(Institute of Technology of Cambodia)で水資源工学と農村インフラストラクチャーの学士学位も取得。2012年の夏に日本福祉大学で開催された世界青少年会議(World Youth Meeting)と、冬にアジア・オセアニア・北米の青少年との交流事業(絆プロジェクト)にカンボジア工科大学より選出されて参加したのを契機に、海外留学を望むようになった。これらの日本への短期研修旅行の後、米国で工学の卒業論文を執筆するための奨学金を受け、半年間の米国留学もした。2015年に日本の文部科学省の修士課程および博士課程の研究生として東京工業大学の土木・環境建設学科に留学するために来日。現在はトンレサップ湖の水環境に関する研究をする傍ら、カンボジア工科大学で講師兼プノンペンのアメリカン大学で環境科学の教員教授として勤めている。
2013年にプノンペン王立大学の外国語学部(IFL)を卒業し、教育専攻の学士号を取得した。2014年にカンボジアの工科大学(Institute of Technology of Cambodia)で水資源工学と農村インフラストラクチャーの学士学位も取得。2012年の夏に日本福祉大学で開催された世界青少年会議(World Youth Meeting)と、冬にアジア・オセアニア・北米の青少年との交流事業(絆プロジェクト)にカンボジア工科大学より選出されて参加したのを契機に、海外留学を望むようになった。これらの日本への短期研修旅行の後、米国で工学の卒業論文を執筆するための奨学金を受け、半年間の米国留学もした。2015年に日本の文部科学省の修士課程および博士課程の研究生として東京工業大学の土木・環境建設学科に留学するために来日。現在はトンレサップ湖の水環境に関する研究をする傍ら、カンボジア工科大学で講師兼プノンペンのアメリカン大学で環境科学の教員教授として勤めている。
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
2019年の最新の国勢調査データの紹介
2024.06.14 特集記事生活情報誌ニョニュム読み物
カンボジア生活情報誌「NyoNyum131号」発行のお知らせ!
2024.06.07 特集記事生活情報誌ニョニュム読み物
安価なお好み焼き「バンチャェゥ」を多くの人に味わってもらえるように夫婦二人で頑張り続けたい!
2024.05.31 カンボジア職業大図鑑「カーロッシー」読み物
今年のクメール正月を思う市民の感想
2024.05.17 特集記事生活情報誌ニョニュム読み物
NyoNyum127号特集①:ニョニュム発行人・山崎幸恵が語る「ニョニュムの生い立ち」
2023.11.28 NyoNyumフリーペーパー出版特集記事
カンボジアで最もモダンで最大級のマツダ自動車ショールーム 正式オープニングセレモニー開催
2023.11.08 イベントニュースビジネス
アンコール見聞録 #38 遺跡を上から見る
2023.09.12 アンコール見聞録シェムリアップ文化
カンボジア生活情報誌「NyoNyum126号」発行のお知らせ!
2023.08.31 NyoNyum